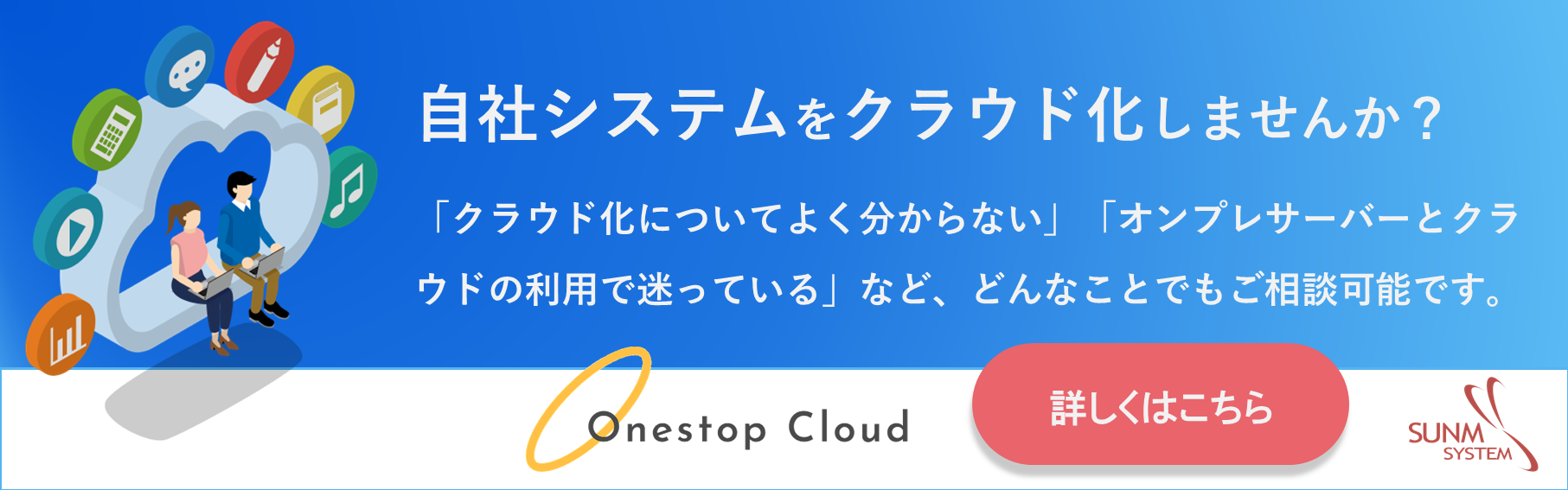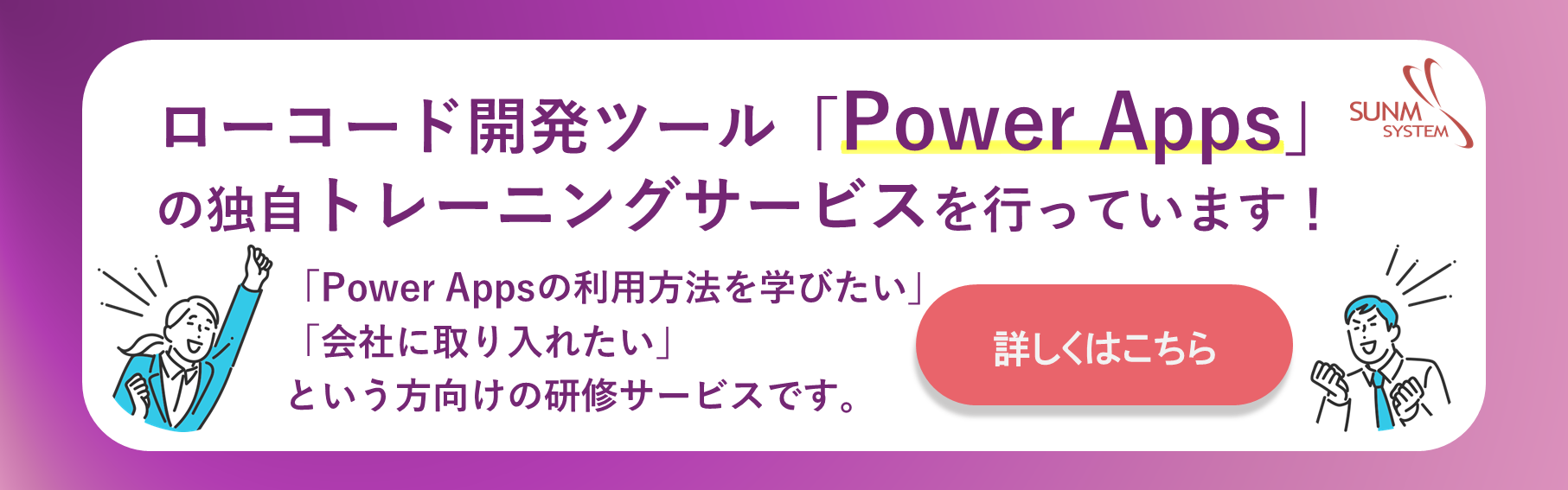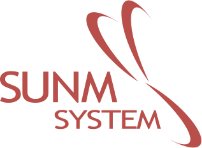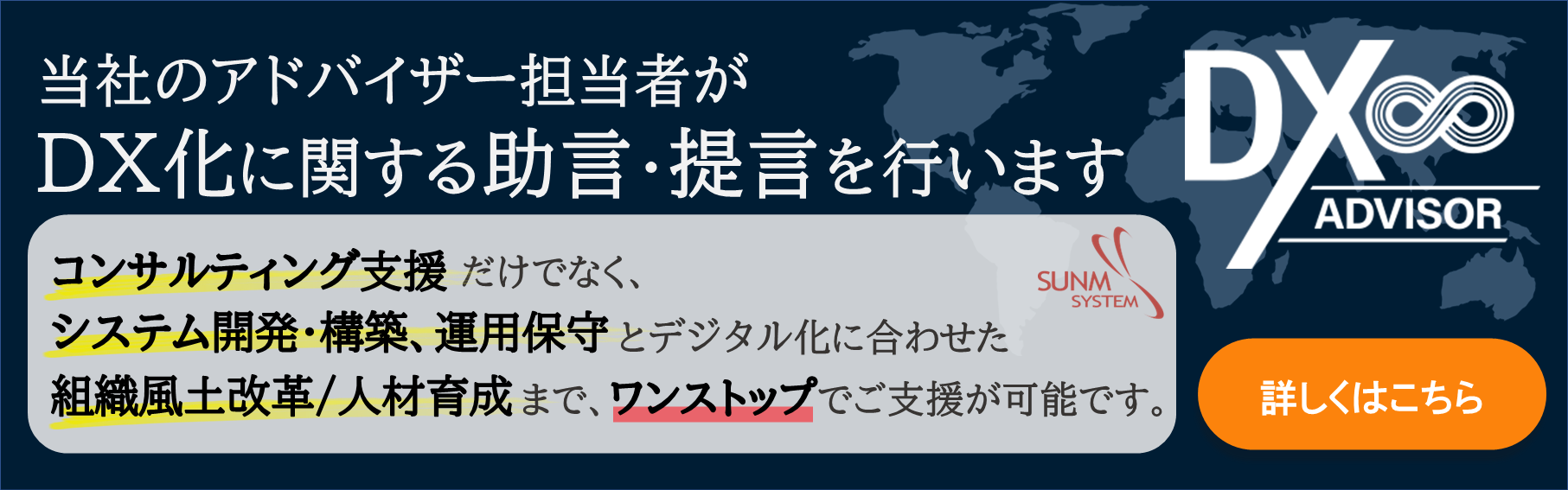⌚ 2025/5/ 8 (Thu) 🔄 2025/5/14 (Wed)
食品DXで実現する製造現場の課題解決と競争力強化 - 成功企業に学ぶ実践アプローチ

食品製造業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、食品安全マネジメント、HACCP対応、アレルギー物質管理など、業界特有の厳格な品質管理要件に加え、人手不足やコスト削減といった課題を解決する可能性を秘めています。本記事では、実際の成功事例を基に、食品製造業に特化したDX推進のポイントと実践的なアプローチ方法を詳しく解説していきます。
製造業のDXについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。
製造業のDXとは?必要性や課題から進め方、成功のポイント、事例まで徹底解説
- DXによる競争力強化と投資判断の指針を求めている食品メーカーの方
- 品質管理の高度化と生産性向上の両立に悩んでいる方
- 品質管理や生産管理におけるDXの具体的な進め方と成功事例を知りたい方
1.食品業界が直面しているDXの必要性
原材料の高騰や人件費の上昇、さらには原産地表示の厳格化や異物混入対策の強化など、食品製造業を取り巻く環境は厳しさを増しています。こうした状況下で企業が持続的に成長するためには、DXによる抜本的な業務改革が不可欠です。
1-1.深刻化する人手不足と品質管理の両立
食品製造現場における人手不足は年々深刻化し、同時にISO22000やHACCPなどの品質管理要件も高度化しています。この相反する課題の解決には、製造現場のDXが不可欠です。
1-2.DXによるプロセス変革の可能性
従来の紙ベースの記録や目視確認に依存した業務プロセスをDXで根本的に見直すことで、リアルタイムな品質管理とデータドリブンな意思決定が実現し、食の安全と生産性向上の両立が可能となります。
1-3.競合他社との差別化における重要性
DXの進展度合いが企業の競争力を左右する時代となり、特に食品製造業では品質保証体制の強化と生産性向上の両立が、市場での優位性確保における重要な差別化要因となっています。
2.製造現場のDX推進で得られる具体的メリット
食品製造現場のDXは、品質管理の自動化、トレーサビリティの強化、生産性向上など、多面的な効果をもたらします。特に食品安全や衛生管理の厳格化に対応しながら、効率性を追求できる点が特徴です。
2-1.品質管理の精度向上とコスト削減の実現
温度・湿度センサーによる製造環境の常時監視、画像認識技術を活用した異物検査、微生物検査の自動化など、デジタル技術を活用した品質管理システムの導入により、検査精度の向上と作業工数の削減を同時に実現できます。
2-2.トレーサビリティによる安全性の担保
原材料の受入れから製造工程、出荷に至るまでの全工程データをデジタル管理し、特にアレルギー物質の混入防止や製造環境データの記録を徹底することで、万が一の問題発生時にも迅速な原因特定と対応が可能となります。
2-3.スマートファクトリー化による製造革新
IoTセンサーによる製造環境のリアルタイムモニタリング、AIによる品質予測、ロボットによる自動化など、製造現場全体をスマート化することで、食品安全と生産効率の両立を実現します。特に清浄度管理や温度管理など、食品製造特有の要件にも対応します。
AIやロボットによる自動化については、次の記事もあわせてご覧ください。
RPAとAIの違いとは?組み合わせて活用する業務改革を解説
3.成功企業から学ぶDX推進のポイント
食品業界におけるDX推進では、各企業が独自の課題に応じた取り組みを展開し、着実な成果を上げています。自社の強みを活かしながら、食品安全マネジメントのデジタル化を基盤とし、データ活用による製品品質の向上と生産性改善を実現しています。現場の理解を得ながら、経営戦略に基づく全社的なDX推進を段階的に進めることが成功の鍵となっています。
DXの成功事例については、次の記事もあわせてご覧ください。
DX成功事例を大企業から中小企業まで業種別にご紹介!共通する成功のポイントとは?
3-1.データ活用による需要予測の最適化事例
日清食品の関西工場では、IoTとロボット技術を活用した次世代型スマートファクトリーとして食品製造における自動化と品質管理の新たな基準を確立しています。 約700台のカメラを統合した集中監視・管理室(NASA室)では、工場内の全情報をリアルタイムで一元管理し、製造工程の完全な可視化を実現しています。15カ所のチェックポイントによる全数検査システムにより、不良品発生率を100万個に1個以下まで低減させることに成功。
さらに、原材料の移動から充填、具材投入までの工程を自動化し、人為的ミスを大幅に削減しています。工場内を清浄度に応じて3段階にゾーニングすることで、徹底した衛生管理体制を構築し、製造データの長期保存によるトレーサビリティも確保。これらの取り組みにより、製品安全性の向上と生産性の大幅な改善を両立させています。
3-2.データ統合による経営改善
カルビーとアサヒグループホールディングスは、原料調達から販売までの収支を一元管理するシステムを構築し、データドリブン経営への転換を実現しています。 S&OP(販売・操業計画)を活用した部門間のデータ共有により、AIによる需要予測の精度を向上させ、在庫の最適化を実現。さらに、品目ごとの収益性分析を通じて、製品ポートフォリオの最適化も可能になりました。アサヒビールでは、統合管理システムの導入により5年間で5億円のコスト削減を見込んでいます。
また、業務プロセスの標準化も同時に進め、グループ全体での経営効率の向上を達成しています。このように、データ統合による収益の可視化と意思決定の迅速化が、企業の競争力強化につながっています。
3-3.データ可視化による製造革新
三島食品では、2020年2月に広島工場にBIダッシュボード「MotionBoard」を導入し、製造現場のデジタル化を実現しています。
工場内の設備や生産ラインと連携したIoTシステムにより、生産状況や実績データをリアルタイムで可視化。生産スケジュール、温湿度管理、設備稼働監視、原材料の品質管理など、多岐にわたる製造データを統合的に管理することで、データ分析時間を最大で10分の1以下に短縮しました。特に原材料の異物検出データの可視化により、産地ごとの品質課題を特定できるようになり、設備保全においてもメンテナンスや部品交換のタイミングをデータに基づいて最適化。これらの取り組みにより、生産性向上と品質管理の強化を実現し、将来的な製造工程の自動制御化への基盤を構築しています。
4.DX推進における課題と解決策
DX推進では技術面だけでなく、製造現場特有の課題への対応が重要です。食品安全マネジメントシステムとの整合性を確保しながら、円滑な導入を実現するためには、段階的なアプローチが効果的です。
DX推進の課題については、次の記事もあわせてご覧ください。
DX推進の課題とは?その解決の方法を解説
4-1.現場の理解を得るためのアプローチ
衛生管理や品質管理の負荷軽減効果を具体的に示し、現場の意見を取り入れながら進めることで、スムーズな導入と定着が可能です。特に、現場スタッフが日々直面している課題に対する具体的な改善効果を示すことで、DX推進への理解と協力を得やすくなります。また、パイロット導入による成功体験の共有も、全社展開における重要なポイントとなります。
4-2.プロセス改革の具体的なステップ
重要管理点(CCP)の特定から始め、モニタリング方法の確立、記録の電子化、自動化という段階を踏むことで確実な変革を実現できます。特にHACCP対応における重要管理点の運用では、デジタル化による記録の正確性向上と作業負荷の軽減を両立することが可能です。各工程での具体的な改善効果を可視化しながら、段階的に展開することが推奨されます。
4-3.システム選定のポイント
食品安全マネジメントの要件に対応し、品質管理システムや生産管理システムと連携可能なソリューションを選定することで、導入後の運用負荷を最小限に抑えられます。特に既存の品質保証体制とのシームレスな統合が重要です。また、将来的な拡張性や他システムとの連携可能性も考慮に入れ、長期的な視点でのシステム選定が求められます。導入後の保守性や運用コストについても事前に十分な検討が必要です。
5.DX推進のロードマップ策定
食品安全と生産性向上の両立を目指し、具体的な実行計画に落とし込むことで、投資対効果の最大化と確実な成果創出が可能となります。
DX推進の進め方については、次の記事もあわせてご覧ください。
DX推進計画とは?企業が着実な変革にいたるための進め方とポイントを解説
5-1.現状分析と目標設定の重要性
現状の品質管理体制と課題を明確にし、食品安全マネジメントの高度化と効率化の両面で実現可能な目標を設定します。単なるシステム導入ではなく、業務プロセスの改善を含めた包括的な視点での分析が重要です。現場の声を丁寧に拾い上げ、解決すべき課題の優先順位付けとそれに基づく具体的な目標値の設定が成功への第一歩となります。
5-2.優先順位付けの考え方
食品安全に関わる重要度と投資対効果を考慮し、品質保証の基盤強化から段階的にDXを推進することで、確実な成果創出が可能となります。特に製品の安全性に直結する工程や人的ミスのリスクが高い作業から優先的に取り組むことで、投資効果の最大化を図ることができます。また、短期的な効果が見込める施策と中長期的な施策のバランスも考慮に入れる必要があります。
5-3.KPI設定と効果測定の方法
品質指標と生産性指標の両面でKPIを設定し、定期的な効果測定を行うことで、継続的な改善活動を推進できます。品質面では不良品率や異物混入件数、生産性面では作業時間や歩留まり率など、具体的な数値目標を設定することが重要です。また、投資対効果を定量的に把握するため、コスト削減効果や省人化効果などの経済的指標も併せて設定します。これらの指標を定期的にモニタリングし、必要に応じて改善施策を講じることで、PDCAサイクルを確実に回すことができます。
6.今後の展望と対応すべき事項
食品業界のDXは今後も進化を続けます。食品安全のさらなる高度化と生産性向上の両立に向け、技術革新への対応と自社の強みを生かした戦略立案が不可欠です。
DXの今後の展望については、次の記事もあわせてご覧ください。
DXの最新トレンドと取り組み状況から成功へのポイントを探る
DXにおける技術の種類とは?課題解決に役立つ情報を解説
6-1.業界トレンドと技術革新への対応
AI画像認識による異物検査、予測型品質管理など、先端技術の進化を見据えた戦略的な投資判断が重要となります。特に食品製造業では、品質や安全性に関わる新技術の採用において慎重な検証が必要です。同時に、製造現場のデジタル化に伴うサイバーセキュリティ対策やデータの利活用に関する法規制への対応なども重要な検討事項となってきています。
6-2.競争優位性の確保に向けた戦略
自社の品質管理ノウハウをデジタル化し、独自の価値創出を目指すことで、持続的な競争優位性を確保できます。製造プロセスのデジタル化で得られたデータを活用し、製品開発や品質改善にフィードバックする仕組みの構築が重要です。また、サプライチェーン全体での最適化を見据え、取引先とのデータ連携や協業体制の構築も検討すべき課題となっています。
6-3.継続的な改善の進め方
データに基づく品質改善と生産性向上のPDCAサイクルを回し、食品製造業としての競争力を継続的に強化します。デジタル化によって得られた知見を組織全体で共有し、人材育成や技術伝承にも活用することが重要です。また、現場からの改善提案を積極的に取り入れ、システムや運用方法の改善を継続的に行うことでDXの効果を最大限に引き出すことができます。さらに、環境負荷低減やフードロス削減など、社会的課題への対応も視野に入れた改善活動の展開が求められています。
7.まとめ
食品製造業のDX推進では、食品安全マネジメントやHACCP対応など業界特有の要件を満たしながら、いかに効率的な生産体制を構築するかが重要です。品質管理の高度化、トレーサビリティの確保、製造環境のスマート化など、さまざまな側面からの取り組みが必要となりますが、すべてを一度に実現しようとするのではなく、自社の状況に合わせた優先順位付けと実行計画の策定が成功への近道となります。
DXによって実現できる価値は、単なる業務効率化にとどまりません。品質保証体制の強化、フードロスの削減、サプライチェーン全体の最適化など、食品製造業ならではの課題解決と新たな価値創造を実現できます。
貴社の状況に合わせた最適なDX推進戦略について、豊富な知見と実績を持つ当社のDXアドバイザーがサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
【この記事を書いた人】
サン・エム・システムコラム編集部でございます。
問い合わせ
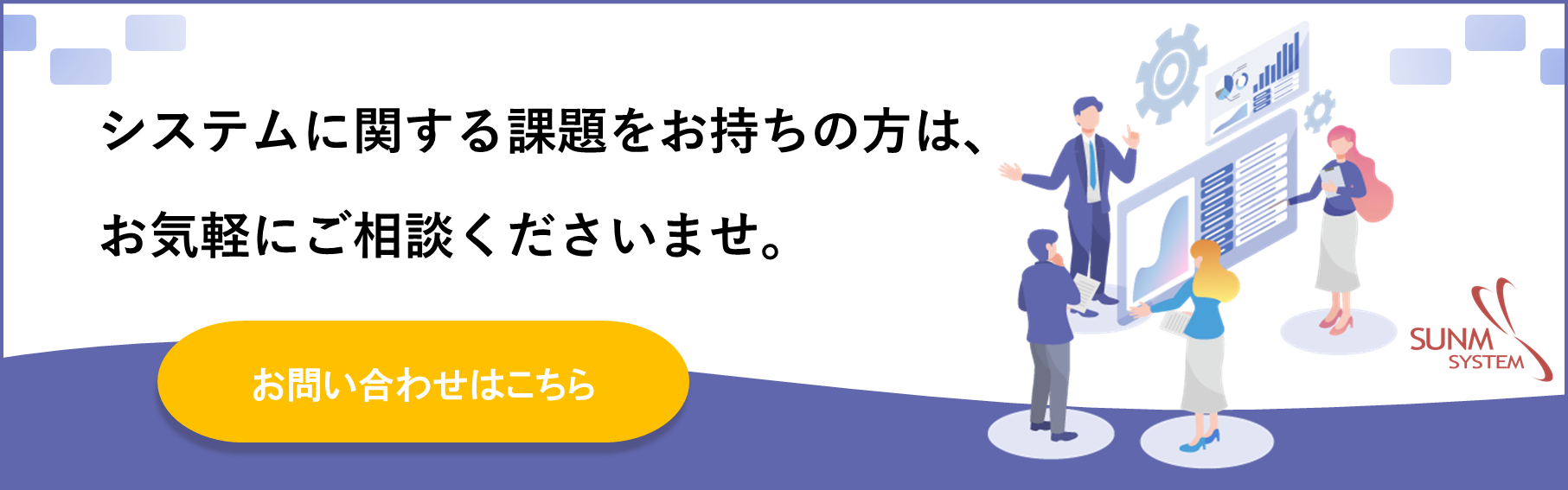
サン・エム・システム サービス