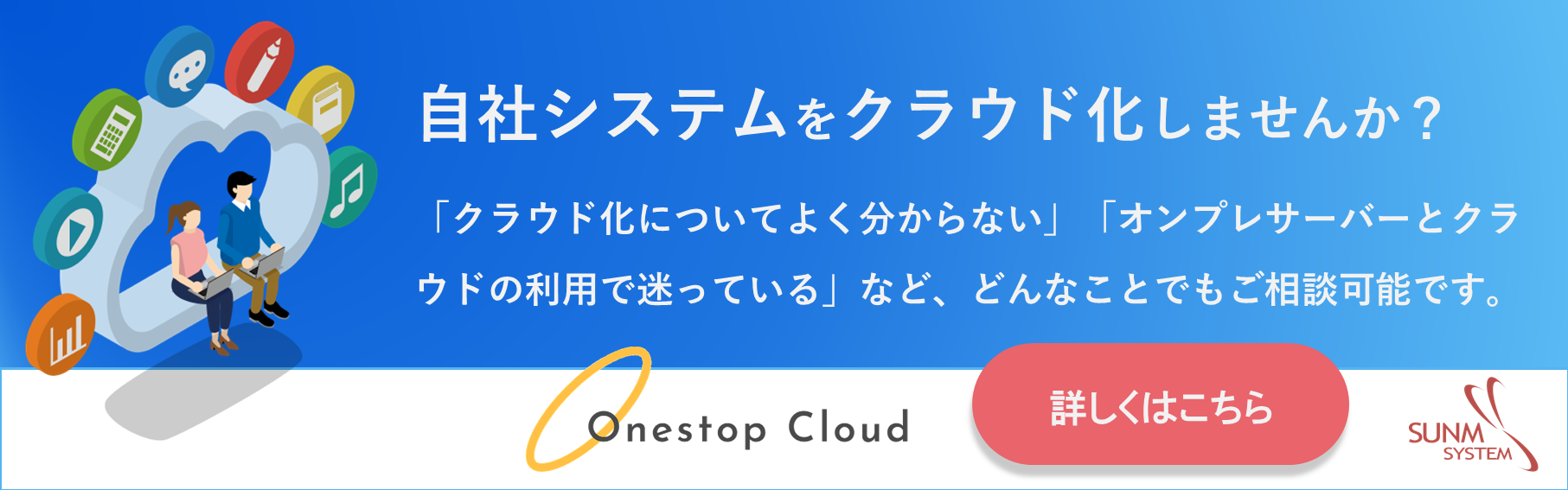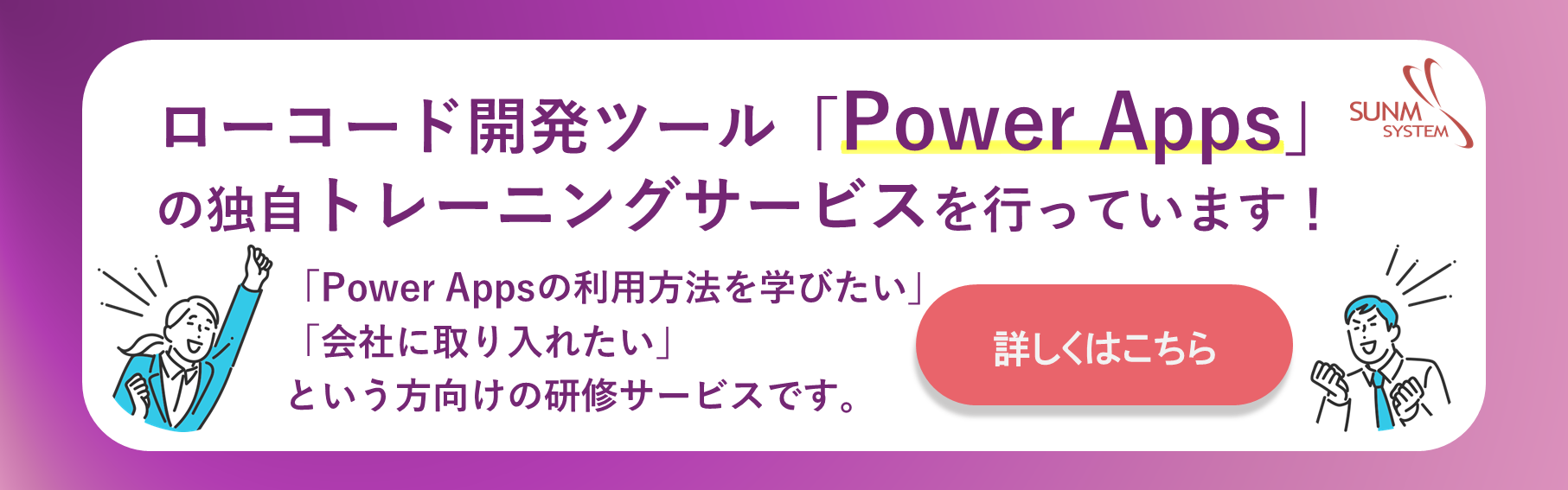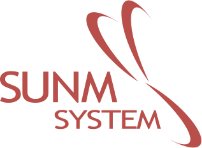⌚ 2025/5/13 (Tue) 🔄 2025/5/19 (Mon)
仕事の属人化が招く退職リスク:IT部門管理職のための脱・属人化実践ガイド
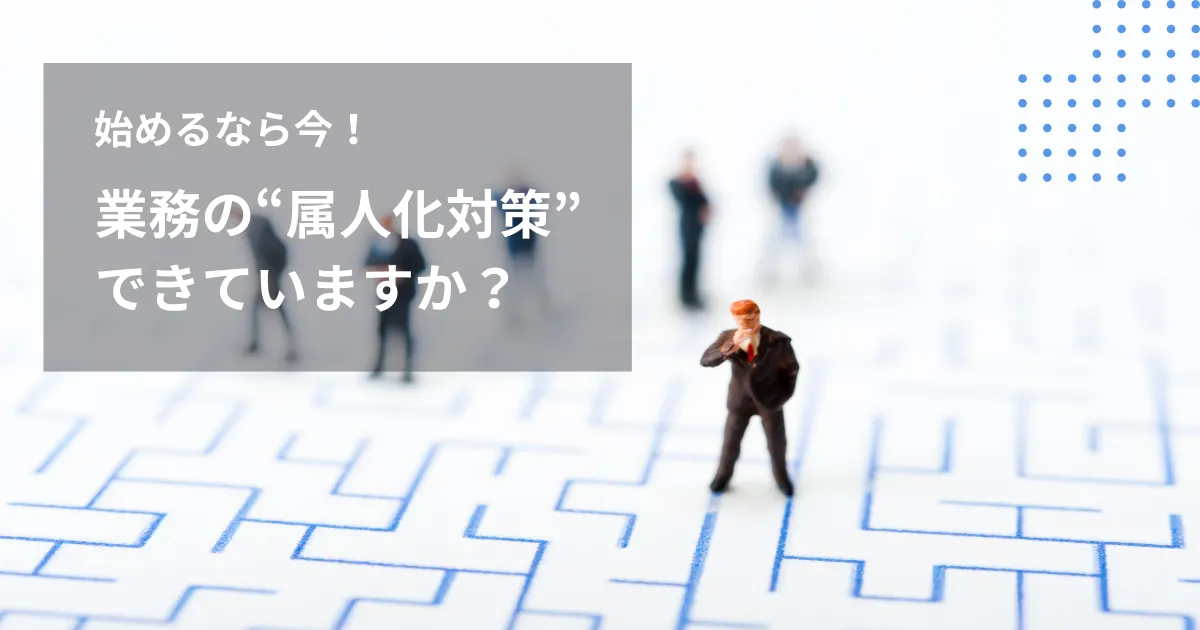
IT企業の情報システム部門では、特定の担当者だけが業務を把握する「属人化」が大きな課題となっています。
担当者の退職によって業務が停滞するリスクはもちろん、属人化自体が退職の原因になることも少なくありません。
本記事では、中堅IT企業の情報システム部門管理職の方々に向けて、属人化の実態と退職リスク、知識・スキルの効果的な移管方法、そして組織的な属人化防止策について具体的に解説します。
- 属人化問題に頭を悩ませている情報システム部マネージャー
- 効率的な引継ぎ方法を模索しているIT部門リーダー
- 属人化を解消して戦略的業務に注力できる体制づくりを目指すIT部門責任者
1.仕事の属人化が情報システム部門にもたらす課題
情報システム部門では、システム開発からインフラ管理、ユーザーサポートまで幅広い業務を担当しています。
特に中堅企業では限られた人材リソースで多様な業務をカバーする必要があるため、自然と特定の担当者に業務が集中しがちです。
属人化した業務は、表面上はスムーズに進行しているように見えますが、その裏ではさまざまな課題が潜んでいます。
担当者が休暇を取ることができない、他のメンバーが業務内容を把握していないため協力体制が築けない、そしてもっとも深刻なのが担当者の退職によって業務が完全に停止してしまうリスクです。
その他の情報システム部門の課題については、以下の記事もあわせてご覧ください。
「情シス(情報システム部門)の課題とは?現状と役立つ解決策を紹介」
2.属人化が進む理由とIT部門特有の要因
属人化が進む理由は複合的です。
まず、業務の専門性と複雑さが挙げられます。
特にレガシーシステムの保守運用や特殊な技術を要するプロジェクトでは、知識やスキルが特定の担当者に集中しやすくなります。
また、IT部門特有の要因として、次のような点が挙げられます。
- 技術の急速な進化により、特定の領域に特化したスペシャリストが必要になる
- ドキュメント作成やナレッジ共有よりも、目の前の問題解決が優先される傾向がある
- 個々の担当者の裁量で業務プロセスが構築されることが多い
- 「この人に聞けば分かる」という組織文化が根付いている
これらの要因が相まって、情報システム部門では他の部門と比較して属人化が進みやすい環境にあります。
3.属人化が招く2つの退職リスク
属人化と退職の関係には、双方向のリスクが存在します。
一方では「担当者の退職による業務停滞リスク」、他方では「属人化自体が退職を誘発するリスク」です。
これらは企業にとって表裏一体の課題であり、相互に影響を与え合う悪循環を生み出す可能性があります。
3-1.担当者の退職による業務停滞リスク
属人化した業務の担当者が退職すると、その影響は広範囲に及びます。
システム障害発生時の対応遅延、開発プロジェクトの中断、日常的なシステム運用の混乱など、部門全体の機能低下につながります。
また、引継ぎが不十分な場合、新たな担当者が業務を習得するまでに長い時間を要し、その間の生産性低下も大きな損失となります。
3-2.属人化自体が退職を誘発するリスク
意外に見落とされがちなのが、属人化が担当者の退職原因になるという点です。
過度な業務負荷によるバーンアウト、「自分しかできない」という精神的プレッシャー、常に対応を求められる状況でのワークライフバランスの崩壊、さらにはキャリア発展の機会喪失など、属人化は担当者にとって大きなストレス要因となります。
4.知識・スキルの効果的な移管方法
知識とスキルの移管は、平時の計画的取り組みと退職決定後の緊急対応の両方が重要です。
日常的なナレッジ共有の文化を築きながら、いざという時の効率的な引継ぎ体制も整えておく必要があります。
特に「暗黙知」の共有を意識し、単なる手順書作成に留まらない総合的なアプローチが求められます。
ここでは、実践的な知識・スキル移管の方法を紹介します。
4-1.ドキュメント文化の醸成
「ドキュメントファースト」の考え方を部門全体に浸透させることが重要です。
新しいシステムの導入時や業務プロセスの変更時には、必ずドキュメントを作成し、更新する習慣をつけましょう。
ドキュメントは単なる手順書ではなく、「なぜそのような設計やプロセスになっているか」という背景情報も含めることで、より価値の高いものになります。
4-2.ナレッジベースの構築
社内Wiki、共有ドライブ、ナレッジ管理ツールなどを活用し、誰でもアクセスできるナレッジベースを構築します。
特に以下の情報を体系的に整理することが効果的です。
- システム構成図と概要説明
- 業務フローとマニュアル
- トラブルシューティングガイド
- FAQ(よくある質問と回答)
- プロジェクト履歴と意思決定の記録
4-3.ペアワークの導入
重要な業務については、主担当と副担当を設定するペアワーク制を導入します。
定期的にローテーションを行うことで、特定の担当者に依存しない体制を構築できます。
開発業務ではペアプログラミングを、運用業務ではシャドーイングを取り入れるなど、業務の特性に合わせた方法を選択しましょう。
4-4.メンタリングプログラムの実施
ベテラン社員から若手社員へ知識やスキルを移管するための公式なメンタリングプログラムを実施します。
定期的なミーティングの機会を設け、業務に関する質問や相談がしやすい環境を整えることで、暗黙知の共有を促進します。
4-5.退職決定後の緊急対応策
担当者から退職の意向が示された場合、限られた時間内で効果的な知識とスキルの移管が必要です。
まず業務の優先度付けを行い、最重要な項目から取り組みます。
具体的な移管スケジュールを作成し、「引継ぎ→実践→フィードバック」のサイクルを計画的に実施します。
詳細なドキュメント作成と並行して、チーム全体での知識共有セッションを開催し、担当者の実演を通じて暗黙知を引き出します。
複数人への分散移管を検討し、新たな属人化を防止することも重要です。
5.属人化を防止するための組織的対策
属人化を根本的に解決するには、組織レベルでの対策が不可欠です。
個人の努力だけでは限界があり、制度や仕組みとして定着させることで持続的な効果を生み出せます。
マネジメント層のリーダーシップと組織全体での意識改革が重要なカギとなります。
以下に具体的な取り組みを紹介します。
5-1.透明性の高い業務プロセスの確立
業務の標準化とプロセスの可視化を進めます。
業務フローを明確に定義し、誰が見ても分かりやすいドキュメントとして整備することで、個人の裁量に依存しない業務運営が可能になります。
また、ツールを活用して業務の進捗状況や課題を可視化することで、チーム全体での情報共有を促進します。
5-2.チームローテーションの実施
定期的な業務ローテーションを実施し、特定の業務が特定の担当者に長期間固定されることを防ぎます。
全てのポジションを一度に変更するのではなく、部分的かつ計画的にローテーションを行うことで、業務の継続性を保ちながら知識の共有を進めることができます。
5-3.評価制度とインセンティブの設計
知識共有や協力体制の構築に貢献する行動を評価する仕組みを導入します。
例えば、ドキュメント作成や後進の育成を評価項目に加えることで、属人化を防止する行動を促進できます。
また、チーム全体の成果に基づくインセンティブを設定することで、個人プレーではなくチームでの協力を重視する文化を醸成します。
人材育成と評価の仕組み作りにお悩みの方には、サン・エム・システムの「G-COMPATH」がおすすめです。
G-COMPATHは、社員一人ひとりの成長を支援する人材育成システムで、組織の成長と個人の成長を同時に実現します。
知識共有やチーム貢献に対する適切な評価基準の設定もサポートし、属人化を防ぐ組織文化づくりに貢献します。
G-COMPATH | サン・エム・システム株式会社
5-4.ITツールの活用
業務管理ツール、ナレッジベース、コミュニケーションツールなど、ITツールを積極的に活用して情報共有を促進します。
タスク管理システムで業務の進捗や担当者を可視化したり、チャットツールで気軽に質問できる環境を整えたりすることで、知識の共有と蓄積を支援します。
属人化を防止するには、ルーチン業務の一部を外部に委託することも効果的な手段です。
サン・エム・システムのヘルプデスクサービスでは、IT資産管理やユーザーサポートなど定型業務を専門スタッフが代行。
情報システム部門の社員がコア業務に集中できる環境を実現し、属人化のリスクを軽減します。
6.脱・属人化でIT部門の生産性を向上させる方法
属人化を解消することは、リスク管理だけでなく、部門全体の生産性向上にも直結します。
業務の分散化により個々のメンバーが専門性を生かせる業務に集中でき、多様な視点による問題解決力とイノベーション創出も促進されます。
さらに、チームワークが強化され、意思決定の迅速化にも寄与します。
以下に具体的なメリットと実現方法を紹介します。
6-1.リソースの最適配分による戦略的業務への注力
属人化を解消することで、特定の担当者に集中していた業務を適切に分散し、各メンバーが自身の専門性を活かせる業務に集中できるようになります。
特に情報システム部門では、日常的な運用管理業務とDX推進などの戦略的業務のバランスが重要です。
運用管理業務の効率化については、以下の記事もあわせてご覧ください。
「IT投資最適化ガイド:情報システム部門が実現する戦略的リソース活用」
6-2.イノベーション促進と問題解決力の向上
多様な視点からの意見交換が可能になることで、イノベーションが促進されます。
属人化された環境では「いつも通り」のやり方が踏襲されがちですが、知識が共有された環境では新しいアイデアや改善提案が生まれやすくなります。
また、複数のメンバーが問題解決に参加できることで、より効率的かつ創造的な解決策を見出せるようになります。
6-3.チームワークと組織文化の改善
「自分の領域」という意識が薄れ、チーム全体で課題に取り組む文化が醸成されます。
お互いの業務内容を理解することで、コミュニケーションがスムーズになり、協力体制が強化されます。
また、「一人で抱え込む」プレッシャーが軽減されることで、メンバーの満足度向上や離職率低下にもつながります。
6-4.意思決定の迅速化
属人化が解消されると、特定の担当者の不在時でも意思決定を進められるようになります。
情報やノウハウが共有されていることで、より多くのメンバーが適切な判断を下せるようになり、部門全体の俊敏性が向上します。
7.まとめ:持続可能なIT部門運営のために
情報システム部門における属人化は、担当者の退職リスクとともに、部門全体の生産性や持続可能性に大きな影響を与えます。
属人化を防止し、知識とスキルを組織全体で共有するためには、以下の取り組みが効果的です。
- ドキュメント文化の醸成と体系的なナレッジベースの構築
- 計画的なチームローテーションとペアワークの導入
- 透明性の高い業務プロセスの確立とITツールの活用
- 知識共有を評価する制度とインセンティブの設計
さらに、ルーチン業務の一部を外部委託することで、戦略的な業務に集中できる環境を整えることも検討に値します。
属人化の解消は一朝一夕に実現するものではありませんが、計画的かつ継続的に取り組むことで、退職リスクを軽減するとともに、より生産性の高い情報システム部門を実現することができます。
情報システム部門の運用管理業務の効率化を検討されている方は、サン・エム・システムのヘルプデスクサービスをぜひご検討ください。
ユーザーサポートやIT資産管理などのルーチン業務を専門スタッフが代行し、コア業務に集中できる環境をサポートします。
【この記事を書いた人】
サン・エム・システムコラム編集部でございます。
問い合わせ
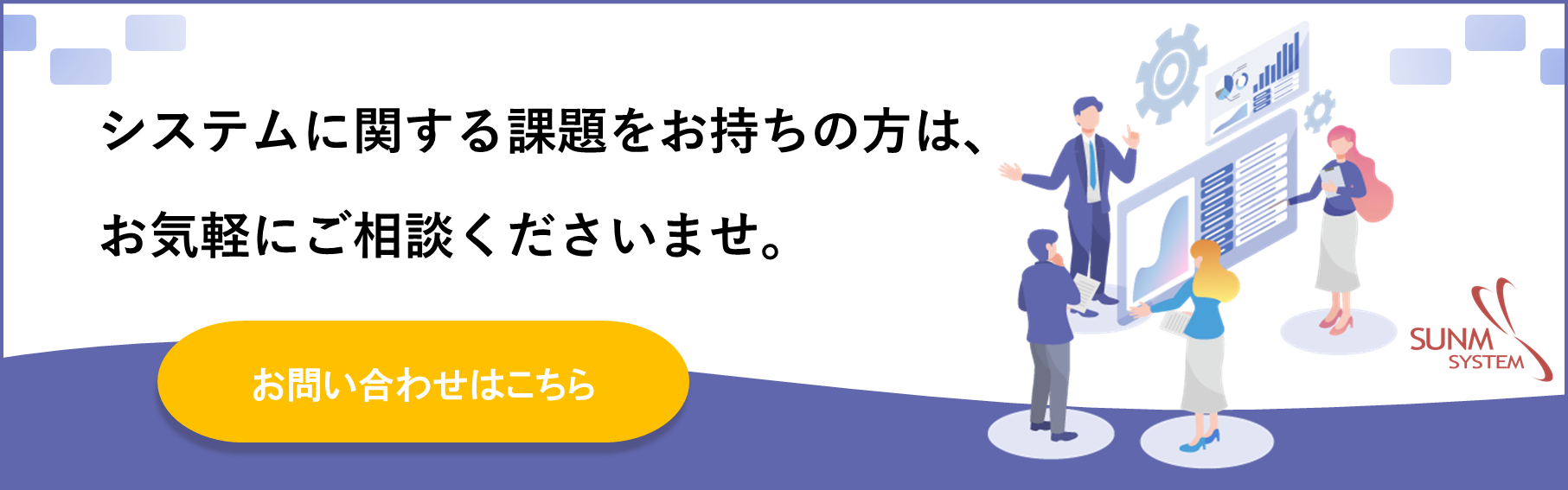
サン・エム・システム サービス